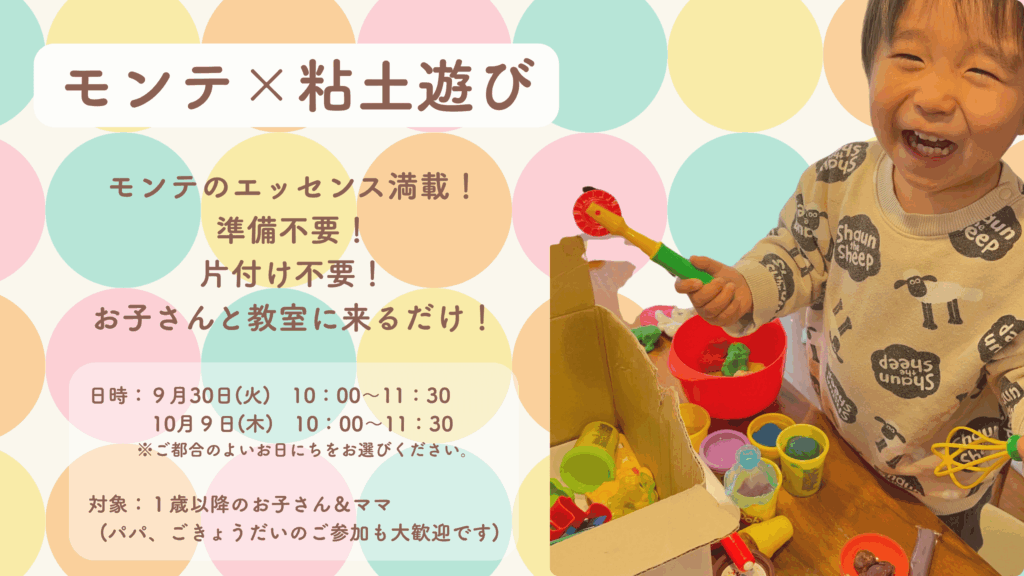【我が子の成長に寄り添うヒント】モンテッソーリ教育の「敏感期」ってなに?

子どもはあっという間に成長していきますよね。気がつくと「昨日までできなかったことが、今日はできるようになってる!」なんてことも多いはず。実はその裏には、**モンテッソーリ教育で大切にされている『敏感期』**という考え方があります。
今回は、子育て真っ最中のママに向けて、敏感期とは何か、どんな種類があるのか、そして家庭でどう活かせるのかを分かりやすくお伝えします。
敏感期とは?
「敏感期」とは、子どもがある特定のことに特に強い関心を示し、自然に学びやすい時期のことです。
例えば、言葉を一気に覚える時期や、小さなものにやたらと気づく時期などがこれにあたります。
この時期に子どもが夢中になることをサポートしてあげると、無理なく力が伸び、自己肯定感も高まっていきます。
主な敏感期の種類と特徴
モンテッソーリ教育では、いくつかの敏感期があるとされています。その中でも、ママが日常で気づきやすい代表例をご紹介します。
1. 言語の敏感期(0〜6歳)
おしゃべりをどんどん覚える時期。
→「これなに?」「どうして?」の質問攻めは、言語の敏感期ならではです。

2. 運動の敏感期(0〜4歳頃)
体を動かすことに夢中になる時期。
→階段の上り下りやジャンプを繰り返すのも自然な姿。
3. 秩序の敏感期(1〜4歳頃)
毎日のルーティンや決まりごとにこだわる時期。
→「このお皿じゃないとイヤ!」も実は成長の証です。

4. 小さなものへの敏感期(1〜3歳頃)
アリや小石など、細かいものにやたらと気づく時期。
→大人には見逃しがちな発見を子どもは楽しんでいます。

5. 社会性の敏感期(3〜6歳頃)
お友達と関わることが大好きになる時期。
→ごっこ遊びや「一緒にやりたい!」という気持ちが芽生えます。
敏感期にどう寄り添えばいい?
ポイントは「やりたい気持ちを尊重して、環境を整えてあげる」こと。
- 言語の敏感期 → 絵本を読んだり、一緒に言葉遊びを楽しむ
- 運動の敏感期 → 安全な公園で思い切り遊ばせる
- 秩序の敏感期 → 毎日の生活リズムをできるだけ守る
- 小さなものの敏感期 → 虫探しや自然散策に出かける
- 社会性の敏感期 → 友達と関わる機会を意識的につくる
「やめなさい!」と止めるのではなく、安心して没頭できる環境を整えてあげることが、成長を後押しします。
まとめ
敏感期は、子どもがぐんと成長するための大切なチャンス。
ママがそのサインに気づいて環境を整えてあげるだけで、子どもの「できた!」が増えていきます。
毎日の子育ては大変ですが、敏感期を知っていると「今はこういう時期なんだ」と心に余裕が生まれますよ。
お母さんの工夫 モンテッソーリ教育を手がかりとして 相良 敦子 著
「早く片づけなさい!」「まだやってないの?」ひっきりなしに、子どもに指示を出していませんか?
ママ、あせらないで! 子育ては、楽しまなくっちゃ。
脳科学に基づくメソッドが、家庭ですぐにできる! 先輩ママの実践レポート多数!
お母さんの「敏感期」 相良 敦子 著
子どもの才能は「敏感期」に決まる。そして、それを発見するのはお母さんのすぐれた観察力。モンテッソーリ教育の第一人者が、その普遍的な部分の教えや技術をわかりやすく解説する基本育児書です。